お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿さんがYouTubeで語った「芸能人やアスリート以外はSNSをやるな」という発言が、大きな波紋を呼んでいます。
発端は、仲の良い芸人・稲田直樹さん(アインシュタイン)のSNSアカウント乗っ取り事件への怒りからでしたが、その言葉が切り取られ「一般人を見下しているのでは」と批判が集中。
動画は削除され、いまもSNS上で議論が続いています。
本記事では、この騒動をめぐる背景と問題点、そしてSNS社会が抱える課題について考えていきます。
そこで今回は、
チョコプラ松尾の炎上騒動の背景
チョコプラ松尾の炎上騒動からみる芸能人と一般人の距離感
SNS社会が抱える誹謗中傷と自由のジレンマ
3つの観点から迫っていきます。
それでは、早速本題に入っていきましょう。
チョコプラ松尾の炎上騒動の背景

松尾さんが問題発言をしたのは、コンビのサブチャンネル「チョコプラのウラ」での一幕でした。
稲田さんのアカウントが不正アクセスを受け、無関係の罪を着せられたことへの怒りを語る中で、
「芸能人やアスリート以外はSNSをやるな。素人が何を発信してるんだ」
と持論を展開。
相方の長田庄平さんが「それじゃ何も流行らない」と突っ込むも、「見てりゃいいんだ」と言い切ったことで火に油を注ぐ結果になりました。
本来の意図は「誹謗中傷を行う人たちへの強い批判」だったと考えられます。
しかし「素人」という言葉選びが、一般人を軽視しているかのように伝わり、「芸能人は特別」という選民意識だと受け止められたのです。
まさに言葉の使い方ひとつが、大きな誤解と炎上を生む典型的な事例でした。
チョコプラ松尾の炎上騒動からみる芸能人と一般人の距離感

今回の炎上を通じて浮かび上がったのは、芸能人と一般人との間に横たわる“距離感”の問題です。
お笑い業界では古くから「素人」という呼び方が使われてきましたが、SNS時代においてはその言葉が持つ意味合いは大きく変わっています。
SNSは芸能人だけの特権ではなく、誰もが情報を発信できる場です。
一般人が日常を共有することがコンテンツとなり、YouTuberやインフルエンサーといった新しい存在も登場しました。
そうした中で「素人は発信するな」という言葉は、時代錯誤にも聞こえ、批判を招いたのです。
脳科学者・茂木健一郎氏も「誰がSNSをやっていいかを決めるのはおかしい」と指摘し、SNSの本質は「表現の自由」にあることを改めて強調しました。
芸能人が無意識に持つ“特権意識”が、いまの社会とズレを生んでしまったといえるでしょう。
SNS社会が抱える誹謗中傷と自由のジレンマ

松尾さんの発言の出発点は「誹謗中傷をなくしたい」という思いでした。
確かにSNSは匿名性が高く、不正アクセスや中傷が絶えません。
実際に稲田さんのように濡れ衣を着せられる被害も起きており、「誰でも発信できる」ことのリスクが浮き彫りになっています。
一方で、SNSは市民一人ひとりにとって大切な発信の場でもあります。
社会問題を告発したり、日常を共有して小さな共感を広げたりすることは、もはや生活の一部です。その自由を奪うことは、民主的な社会に逆行する危険性があります。
つまり私たちが直面しているのは「表現の自由」と「誹謗中傷対策」のせめぎ合いです。
今回の騒動は、芸能人の不用意な発言が引き金となり、SNS社会全体が抱える矛盾を改めて浮かび上がらせたといえるでしょう。
まとめ
チョコプラ松尾さんの「素人はSNSをやるな」発言は、文脈を無視して拡散された部分もありますが、言葉選びのミスによって「選民意識」「時代錯誤」という批判を招きました。
SNSは誹謗中傷の温床であると同時に、誰もが自由に意見を発信できる場です。
この両面性をどう扱うかは、私たち全員に突きつけられた課題です。
芸能人であれ一般人であれ、言葉の影響力を意識し、誹謗中傷ではなく建設的な発信を心がけること。
それこそが、自由なSNS社会を守るために求められる姿勢なのではないでしょうか。
それでは、ありがとうございました!
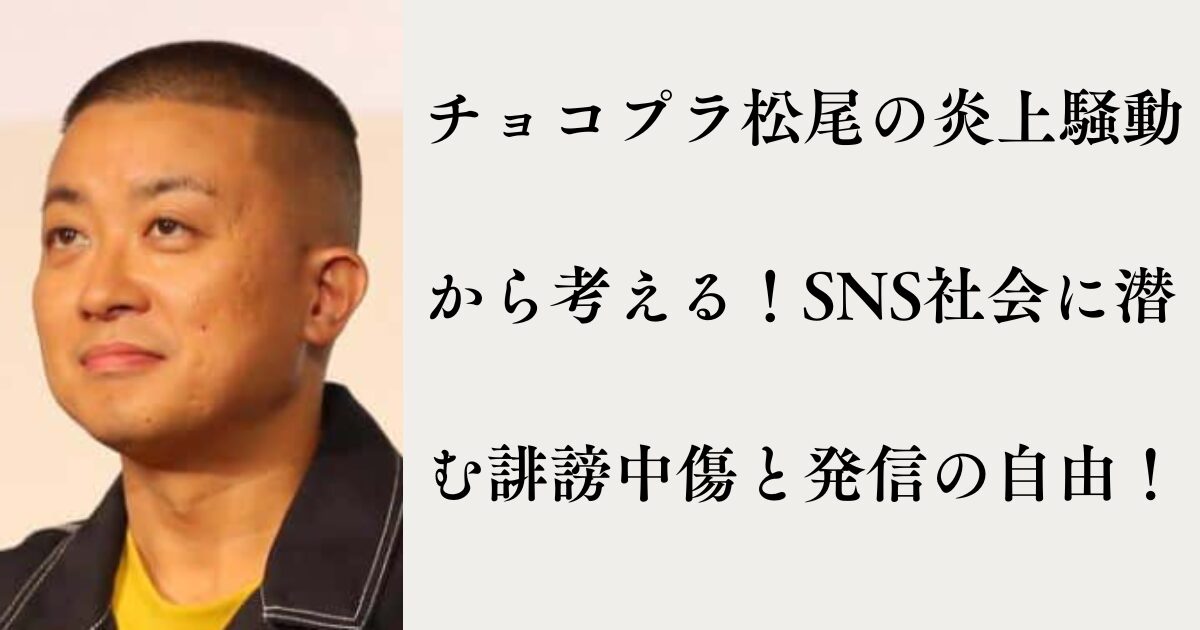
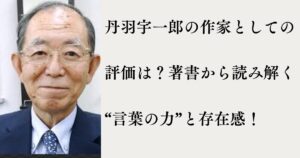
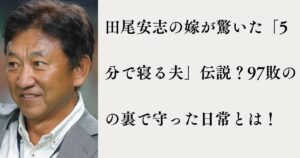
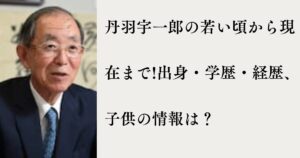
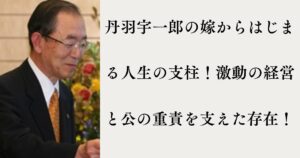
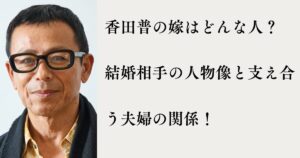
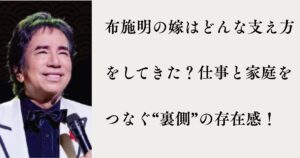
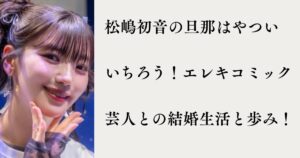
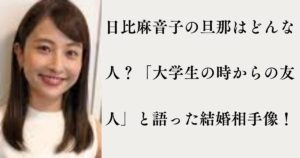
コメント