2002年、長野県政に前代未聞の激震が走りました。
作家出身の知事・田中康夫が掲げた「脱ダム宣言」により、県議会との対立が激化。ついには不信任決議可決という異例の事態に発展します。
しかし――その後の「出直し選挙」で県民は再び田中氏を選び、全国の注目を集めました。
今回は、「不信任」と「脱ダム」をめぐる長野県政の真実をわかりやすく振り返ります。
そこで今回は、
「脱ダム宣言」とは田中康夫が挑んだ構造改革
田中康夫の議会との衝突――2002年「不信任決議」の真実
田中康夫の出直し選挙と再選――県民が選んだ「脱ダム」の意思
3つの観点から迫っていきます。
それでは、早速本題に入っていきましょう。
「脱ダム宣言」とは田中康夫が挑んだ構造改革
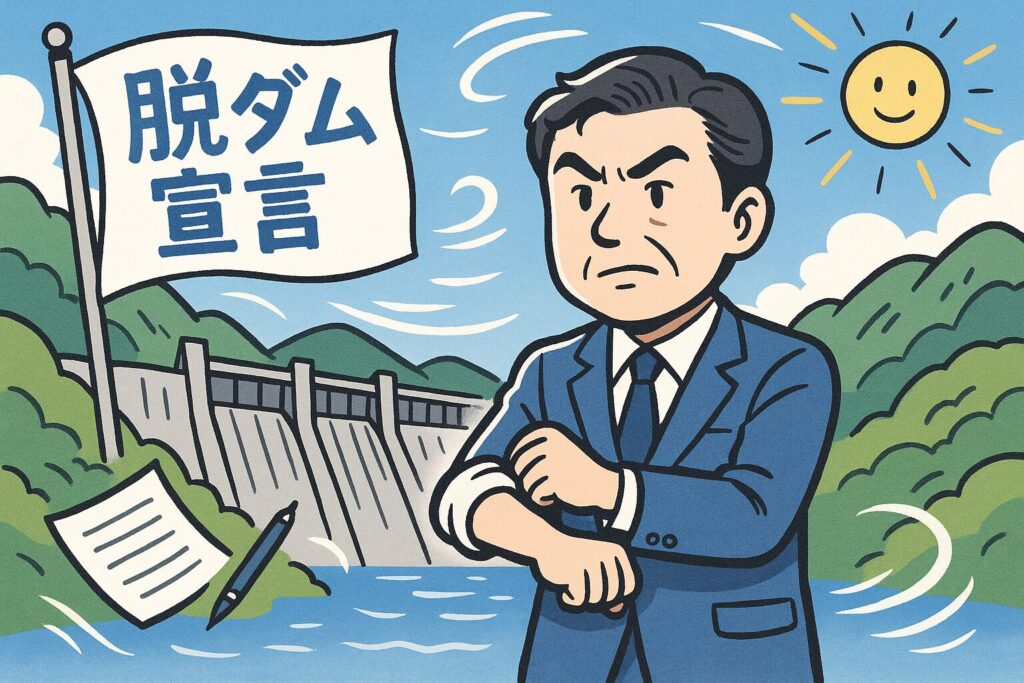
2001年、作家としても知られる田中康夫氏は、長野県知事に就任。
彼が最初に打ち出したのが、公共事業の象徴だった**「脱ダム宣言」**でした。
長野県は当時、多くのダム計画を抱えており、巨額の建設費が問題視されていました。
田中氏は「ムダな公共事業に頼らない県政」を掲げ、既存のダム計画を全面的に見直すと発表。
この方針は、地方自治のあり方を根本から問い直すものでした。
しかし、長年の利害関係が絡むダム事業の中止は、県議会や建設業界、地元自治体との激しい対立を生むことになります。
田中康夫の議会との衝突――2002年「不信任決議」の真実
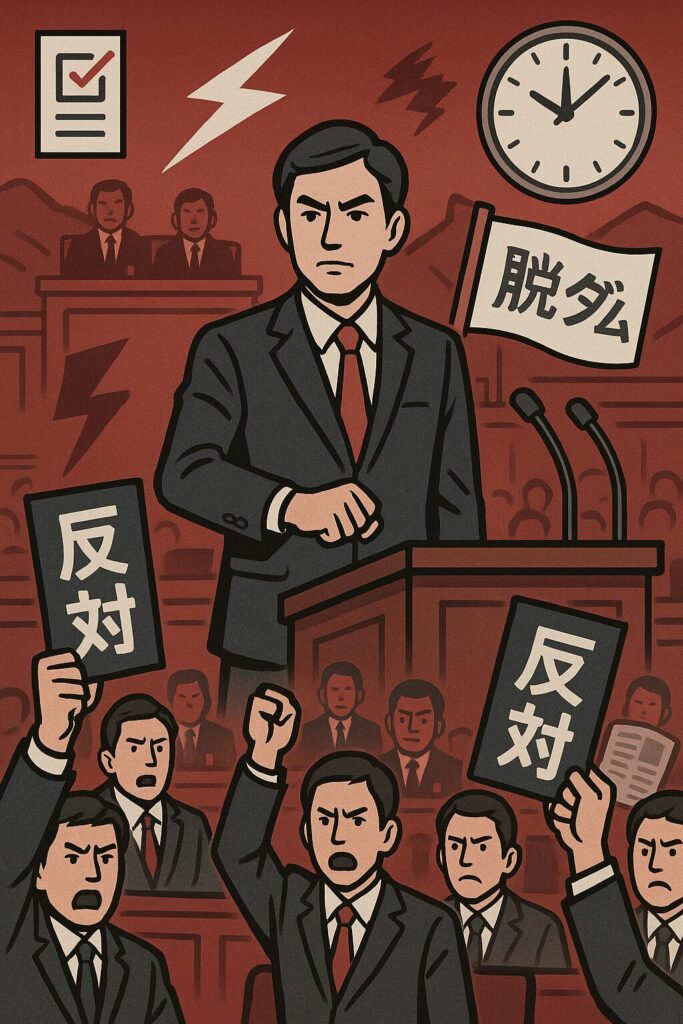
「脱ダム」をめぐる議会との対立は、次第に激化していきました。
県議会は、知事の独断的な姿勢を「議会軽視」と非難。
そして2002年7月5日、ついに「田中康夫知事不信任案」を賛成44・反対5で可決します。
田中氏は「議会解散」か「失職」のどちらかを選べる立場にありましたが、自らの信念を貫くため、あえて失職の道を選択。
この決断は、県民の大きな関心を呼びました。
メディアでは「県民 vs 議会」の構図として連日報道され、長野県は一気に全国の注目を集めることになります。
田中康夫の出直し選挙と再選――県民が選んだ「脱ダム」の意思

不信任によって失職した田中康夫氏は、すぐに**出直し知事選(2002年9月1日)**へ出馬。
対立した県議会側は複数候補を擁立しましたが、結果は――田中康夫が圧勝。
この再選は、「脱ダム」政策への県民の理解と支持が明確に示された瞬間でした。
彼の政治手法は全国に影響を与え、以後の地方自治のあり方や、公共事業の見直しにも波及します。
不信任を乗り越えた田中康夫の姿は、まさに“民意の象徴”として語り継がれています。
まとめ
田中康夫の「脱ダム」政策は、単なる公共事業の見直しではありませんでした。
それは「地方自治は誰のためにあるのか」「政治は誰が決めるのか」という問いを突きつけた改革だったのです。
不信任という試練を経て、彼は県民の信頼を得て再び知事となりました。
その姿勢は今なお、**“信念を貫く政治家像”**として語り継がれています。
それでは、ありがとうございました!
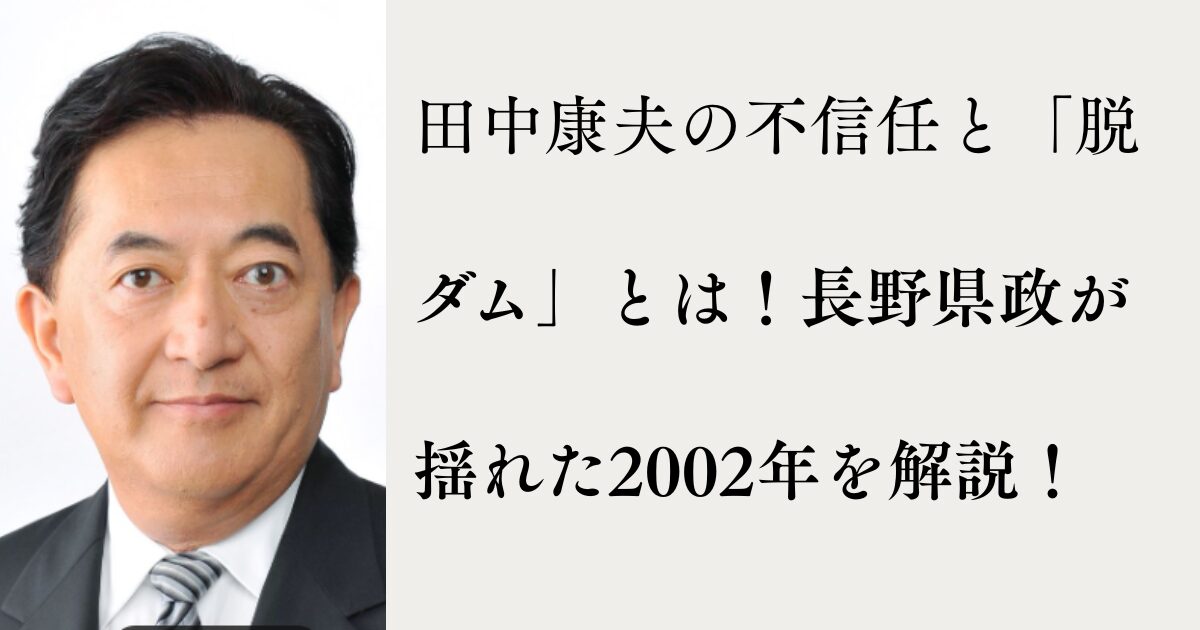
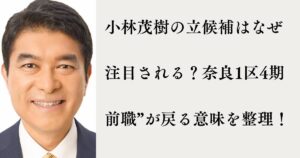
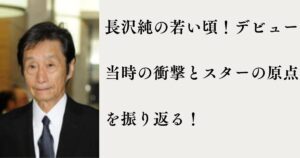
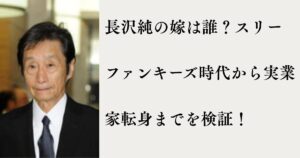
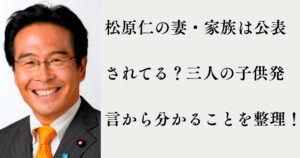
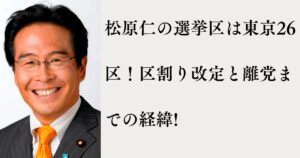
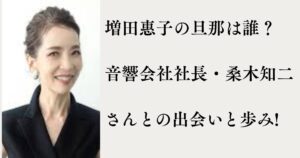
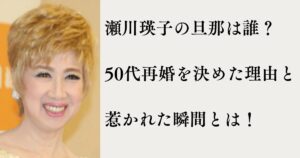
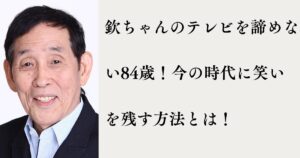
コメント