近年、企業にとって従業員の離職は避けて通れない課題となっています。
人材不足が叫ばれる中、「辞める社員をどう扱うか」は経営者や管理職にとって大きな悩みの種です。
引き止めるべきか、それとも快く送り出すべきか――。
その答えを模索する中で、多くの経営者が学びの源泉としてきたのが「経営の神様」と呼ばれた稲盛和夫氏です。
彼が貫いた「去る者は追わず」という姿勢には、単なる無関心ではなく、深い経営哲学と人間観が込められていました。
そこで今回は、
稲盛和夫の離職哲学の「去る者は追わず」という理念の背景
京セラ創業期に見せた厳しさと愛情
稲盛和夫の離職哲学の現代企業への示唆
3つの観点から迫っていきます。
それでは、早速本題に入っていきましょう。
稲盛和夫の離職哲学の「去る者は追わず」という理念の背景

「来る者は拒まず、去る者は追わず」という言葉は古代中国の思想家・孟子の教えに由来します。
人が自ら近づいてくれば受け入れ、去るのであればその意志を尊重するという考え方です。
稲盛和夫氏もこの姿勢を経営の中に取り入れましたが、彼の実践は単純な寛容さとは異なっていました。
稲盛和夫氏にとって、会社はただの雇用の場ではなく「人生を共に築く仲間の集まり」でした。
だからこそ、辞めていく従業員を単に同情したり慰めたりすることは、本人の決断を軽視することにつながると考えたのです。
むしろ、自らの選択に責任を持たせることこそが、真にその人の未来を思いやる行為であるという信念がありました。
京セラ創業期に見せた厳しさと愛情

1968年、京セラ創業間もない頃の出来事が象徴的です。
入社から半年足らずで「辞めて板前になりたい」と言い出した若者に対し、稲盛和夫氏はまず「料理の道も甘くはない」と真剣に諭しました。
しかし、最終的に本人の意思が固いと分かると、同情や慰めをかけることなく送り出したのです。
この態度を見た一部の社員は「大家族主義といいながら冷たい」と批判しました。
しかし稲盛氏は怒りをもって反論し、「会社を否定して辞めていく者に、どう同情せよというのか」と断言しました。
そこには、安易な慰めではなく「人生を自ら切り拓く覚悟を持て」という強い教育的意図が込められていました。
稲盛和夫の離職哲学の現代企業への示唆

稲盛和夫氏の「去る者は追わず」は、現在の人材マネジメントにおいても大きな示唆を与えます。
引き止めや慰留は時に必要ですが、それが本人の覚悟や自由を奪うこともあります。
むしろ、退職という決断を尊重し、そこから学びを得ることで組織も成長できるのです。
同時に、稲盛氏の姿勢は「冷たい拒絶」ではなく「本人の未来への信頼」でもありました。
自ら選んだ道を歩む者には、同情ではなく静かに見守る強さを持つ――。
それが本物のリーダーシップであり、企業の文化を豊かにする要素となるのではないでしょうか。
まとめ
稲盛和夫氏の離職哲学「去る者は追わず」は、単なる消極的態度ではなく、社員一人ひとりの人生に責任を持たせるための厳しくも温かい姿勢でした。
辞める者に同情するのではなく、その決断を尊重する。
そこには、社員を「仲間」として信じる深い愛情と、経営者としての揺るぎない信念が込められていたのです。
現代の経営者にとっても、この哲学は人材の流動化が進む時代において重要な指針となるでしょう。
それでは、ありがとうございました!

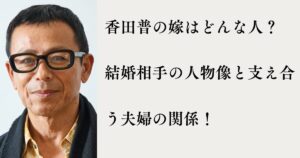
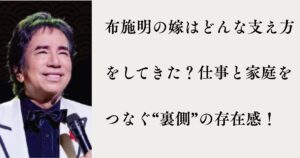
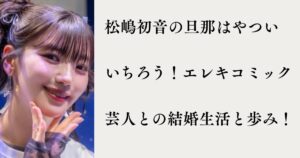
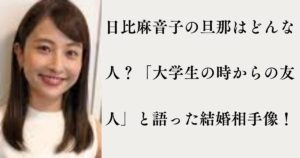
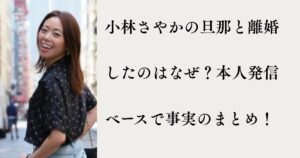
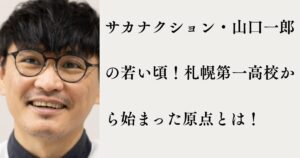
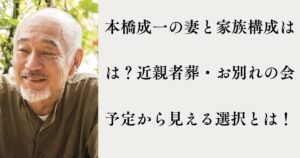
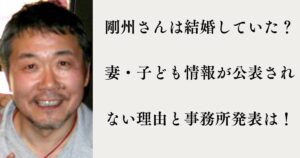
コメント