舞踊家であり俳優としても活躍する田中泯さん。
日本の芸術界において独自の存在感を放つ彼ですが、その表現の根底には「若い頃の海外体験」が大きく影響しています。
特に1970年代、ニューヨークに渡った経験は、彼の舞踊哲学を形づくる重要なきっかけとなりました。
今回は、田中泯さんの若き日の挑戦とニューヨークで得た表現の自由について詳しく見ていきましょう。
そこで今回は、
田中泯の若い頃の背景と模索
田中泯のニューヨークで出会った前衛的ダンスシーン
田中泯の海外体験がもたらした独自の舞踊哲学
3つの観点から迫っていきます。
それでは、早速本題に入っていきましょう。
田中泯の若い頃の背景と模索
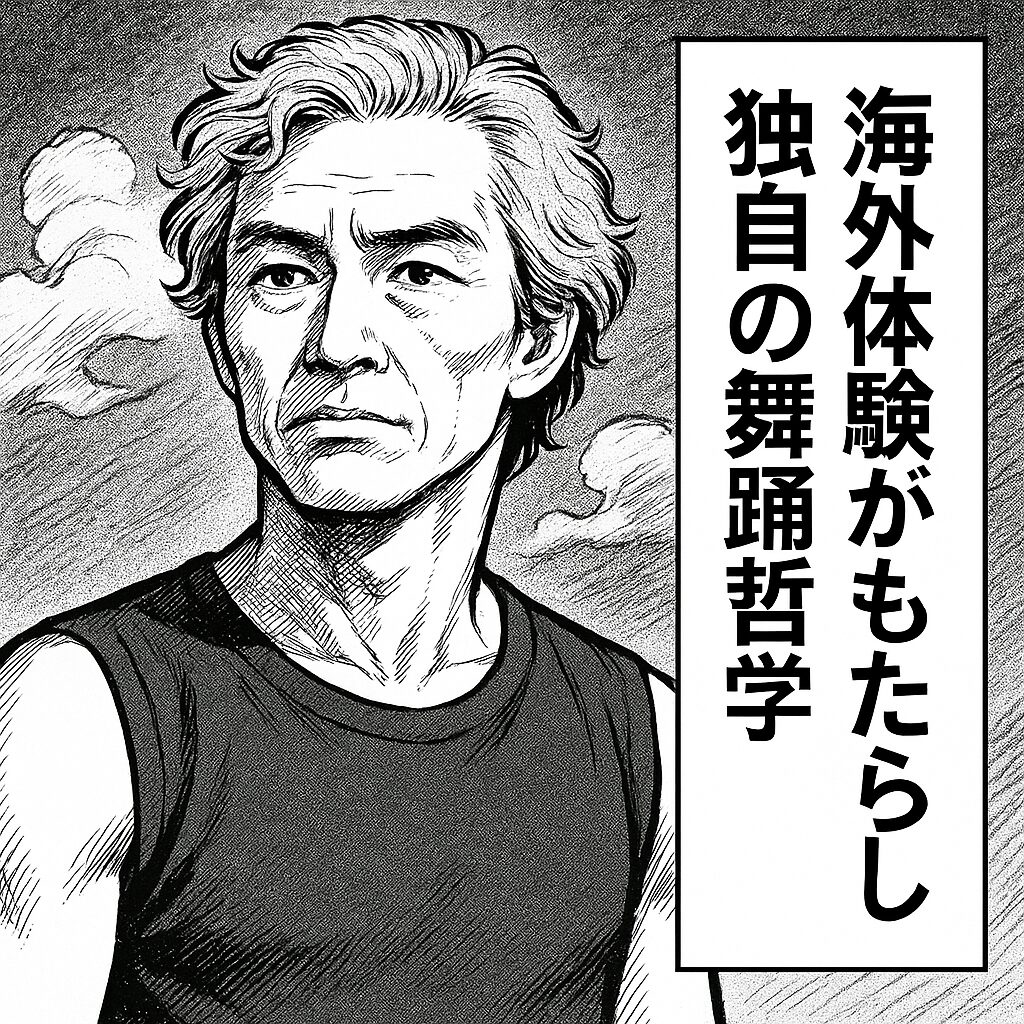
1945年、東京都に生まれた田中泯さん。
1945年3月10日、東京大空襲の日に生まれた田中泯は、東京・八王子の里山近くで育った。
出典:PANJ
学生時代には体操に励み、身体を自由に使う感覚を早くから身につけていました。
20代になるとクラシックバレエやモダンダンスを学びますが、既存の型に従うことへの違和感が常につきまとっていたといいます。
バレエのスタジオに見学に行ったんです。理由は簡単で、幼少期に盆踊りに出会って以来、大好きだった踊りを正式に習うにはどうしたらいいかと考えたからなんです。
出典:実演家著作隣接権センター
当時の日本の舞踊界は欧米から輸入されたスタイルを模倣する傾向が強く、独自性を追求する場は限られていました。
その中で田中さんは、「自分の身体とは何か」「踊るとは何を意味するのか」を問い続ける日々を送ります。
やがてその探求心は、日本を飛び出して海外で答えを探そうとする原動力となっていきました。
田中泯のニューヨークで出会った前衛的ダンスシーン

1970年代、田中泯さんはニューヨークへ渡ります。
当時のニューヨークは、アートやダンスにおいて実験的な試みが盛んな都市でした。
1970年代以降、裸体の前衛ダンサーとして芸術の中心地であるパリ、ニューヨークをはじめ、東欧諸国から東南アジアに至るまで数多くの都市・地域で踊り、常にセンセーションを巻き起こしてきた。
出典:実演家著作隣接権センター
モダンダンスやコンテンポラリーダンスはもちろん、即興性を重視したパフォーマンスや、街中で行われるストリート的な表現まで、多様なスタイルが入り混じっていました。
田中さんはそこで「踊りは舞台の上だけで成立するものではない」という考えに触れます。
自然や都市、日常生活そのものを舞台にできること、そして身体そのものが表現の原点であることを強く実感したのです。
型にとらわれない表現に出会ったことは、彼にとって大きな衝撃であり、束縛から解き放たれるような感覚をもたらしました。
また、異国の地でさまざまなアーティストと交流する中で、自分の身体表現が世界に通用するかどうかを試す場ともなりました。
日本で感じていた閉塞感を打ち破り、ニューヨークは田中泯さんに「表現の自由」を与えてくれたのです。
田中泯の海外体験がもたらした独自の舞踊哲学

ニューヨークでの経験を経て帰国した田中泯さんは、既存の舞踊の枠に収まらない表現を追求します。
代表的なのが「ハイテクノロジーと身体」「自然と人間」といったテーマを背景にした独自の舞踊活動です。
田中さんは「踊りとは踊ることそのものではなく、身体を通じて世界とつながる行為」と語っています。
これはニューヨークで出会った自由な芸術環境がなければ生まれなかった発想でしょう。
彼の舞踊は観客に“美しい動き”を見せるものではなく、人間存在の根源を問いかけるものとして進化していきました。
さらに、この哲学は俳優としての演技にも活かされています。
映画『たそがれ清兵衛』や大河ドラマなどで見せる存在感には、単なる演技を超えた「身体そのものの表現」がにじみ出ています。
その背景には、若い頃に培われた海外での挑戦が息づいているのです。
まとめ
田中泯さんの若い頃の海外体験、特にニューヨークでの時間は、彼にとって単なる留学や修行の場ではありませんでした。
それは既成の価値観から解き放たれ、自らの身体と向き合い続ける出発点となるものでした。
ニューヨークで得た「表現の自由」は、帰国後の舞踊活動に深く根ざし、その後の芸術活動や俳優としてのキャリアにまで影響を与えています。
彼の独自の存在感の裏には、若き日に異国で挑戦した経験があったのです。
それでは、ありがとうございました!
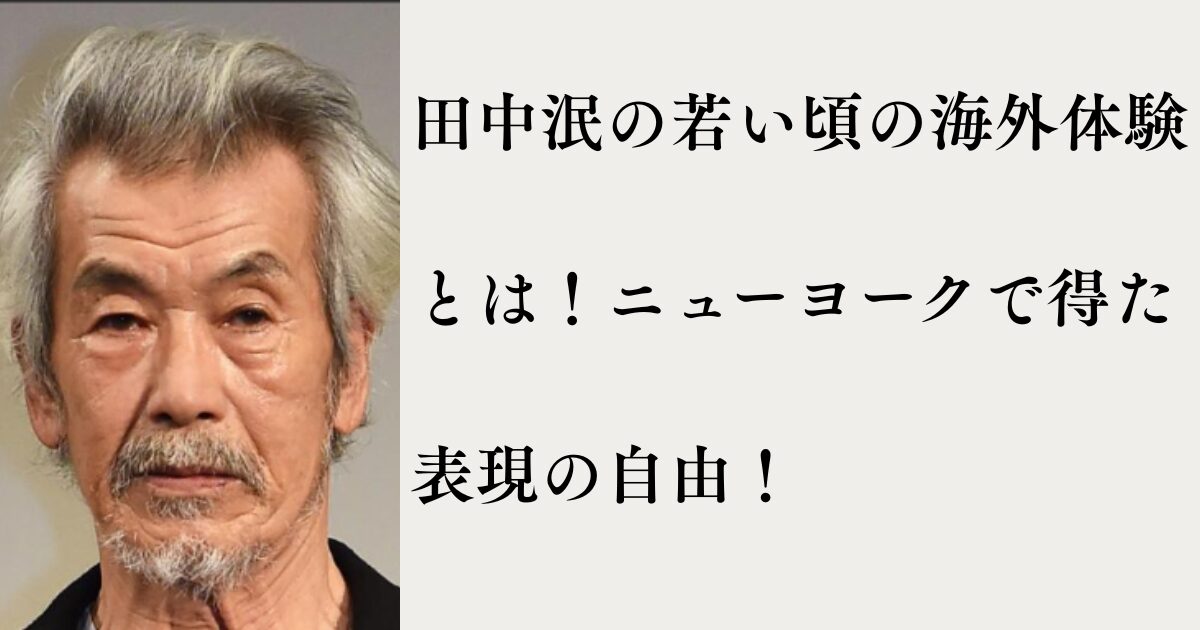
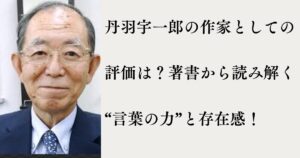
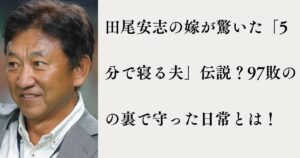
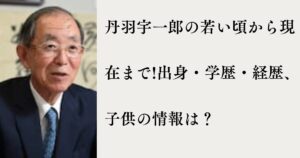
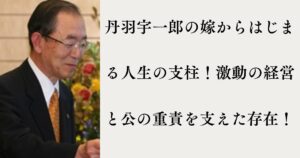
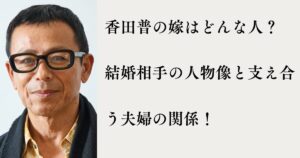
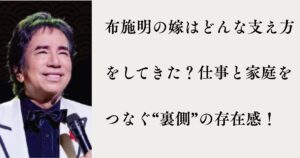
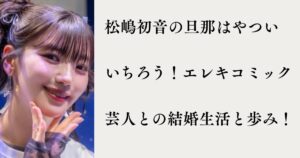
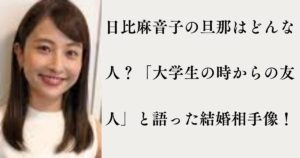
コメント