2024年2月、俳優の佐藤二朗さんが自身のX(旧Twitter)で「強迫性障害(OCD)」を患っていることを公表し、多くの人々の注目を集めました。
ユニークな演技と独特なキャラクターで知られる佐藤さんが、実は長年精神的な病と向き合ってきたことに驚きと共感の声が広がりました。
本記事では、佐藤さんの強迫症との向き合い方、創作活動への影響、そして社会へのインパクトについて掘り下げていきます。
そこで今回は、
佐藤二郎の強迫性障害は小学生の頃から
佐藤二郎の映画『memo』に込めた想いとメッセージ
佐藤二郎の強迫性障害の社会に与えた反響と理解
3つの観点から迫っていきます。
それでは、早速本題に入っていきましょう。
佐藤二郎の強迫性障害は小学生の頃から

佐藤二朗さんが強迫性障害を患い始めたのは、小学生の頃。本人は2024年2月6日の投稿で次のように語っています。
自身の病気について「強迫性障害」だと告白。「小学生時に発症」と説明す、「あまりにキツく『memo』という映画をつくる。根治を諦め、共生を決める。
出典:スポニチ
この言葉から、長年にわたって症状と向き合い、完治ではなく「共生」を選んだことが分かります。
強迫性障害とは、不安や恐怖に駆られて繰り返し確認や行動をしてしまう精神疾患の一種で、周囲には理解されづらい特性があります。
例えば、「手を何度も洗う」「鍵の施錠を何度も確認する」「頭の中で同じ言葉を繰り返す」といった行動が知られています。
佐藤さんもこうした症状に悩まされながら、俳優としてのキャリアを築いてきたのです。
佐藤二郎の映画『memo』に込めた想いとメッセージ

2008年に公開された佐藤二朗さんの初監督作品『memo』は、まさに自身の体験をもとに制作された作品です。
主人公は強迫性障害を抱える女子高生で、日常の中で葛藤しながらも、周囲と少しずつ心を通わせていく様子が描かれています。
役として強烈な個性を発揮する俳優・佐藤二朗が“強迫性障害”という自身の経験を基にした物語で監督デビュー。同じ病を抱えた女子高生と中年男との交流を描くドラマ。
出典:MOVIE MALKER
この映画について佐藤さんは、「自分の病気を“描く”ことで救われた部分がある」と語っています。
つまり、創作という行為そのものが、自身の症状と向き合う手段であったのです。
また、映画を通じて「この病気に悩む人がひとりじゃないと伝えたい」という思いも込められていました。
佐藤二郎の強迫性障害の社会に与えた反響と理解

佐藤二朗さんの告白は、同じく強迫性障害を抱える人々にとって大きな励ましとなりました。
「自分だけじゃない」「あの佐藤二朗さんも苦しんでいたんだ」と感じた人は少なくありません。
SNS上では、
「勇気をもらった」
「私も病と向き合ってみようと思えた」
「映画memoを見直したくなった」
といった声が多数寄せられ、精神疾患への理解を深める契機となりました。
また、精神疾患に対するスティグマ(偏見)が根強く残る社会において、著名人が自ら語ることは大きな意義があります。
佐藤さんのように自分の病を隠さず伝える姿勢は、他者の「理解するきっかけ」となり、社会全体の意識改革へとつながります。
まとめ
佐藤二朗さんが公表した「強迫性障害」という言葉。
その一言には、長年の葛藤、痛み、そして希望が込められていました。
彼はただ病と戦っているだけではありません。
病を受け入れ、時には創作の糧に変え、自分らしく生きる道を選びました。
その姿勢は、私たちに「弱さを隠さずともいい」「苦しみを共有していい」と教えてくれます。
精神的な病に悩むすべての人にとって、佐藤さんの言葉と行動は大きな光となるでしょう。
そして社会においても、こうした告白がもっと自然に受け止められる未来を目指すことが求められています。
それでは、ありがとうございました。
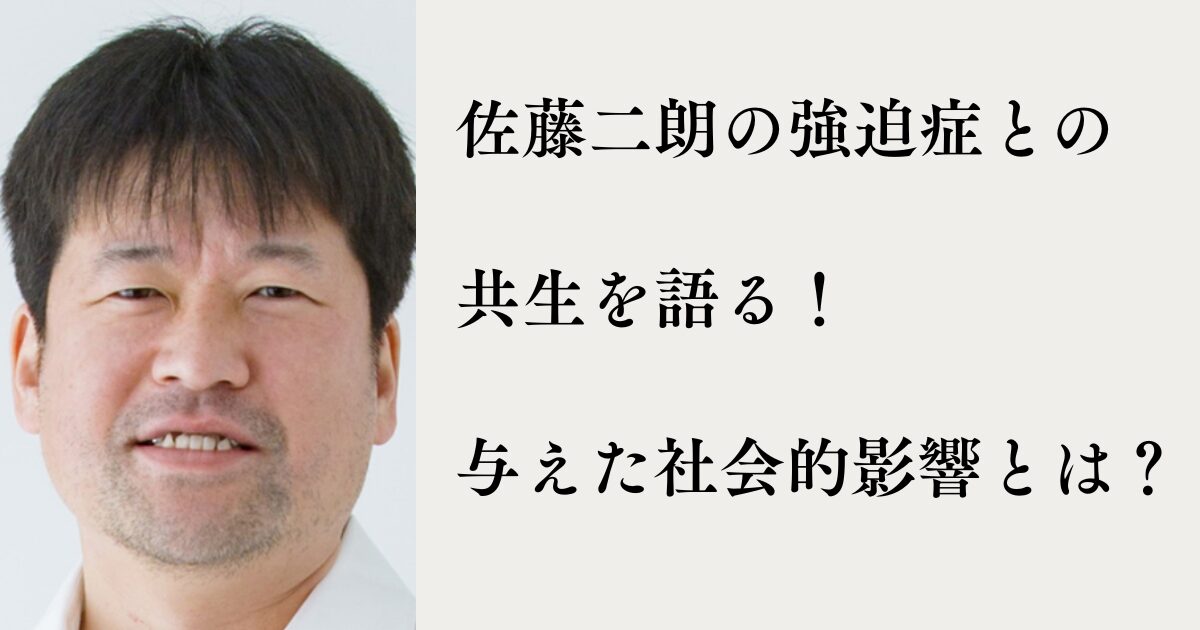
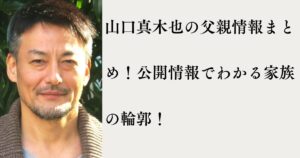
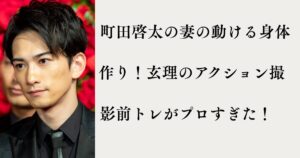
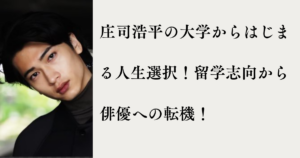
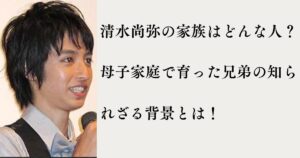
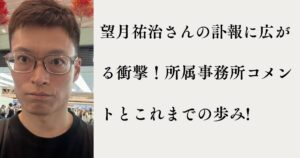
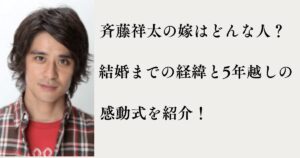
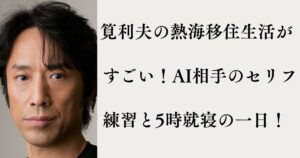
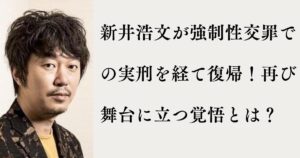
コメント